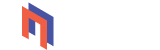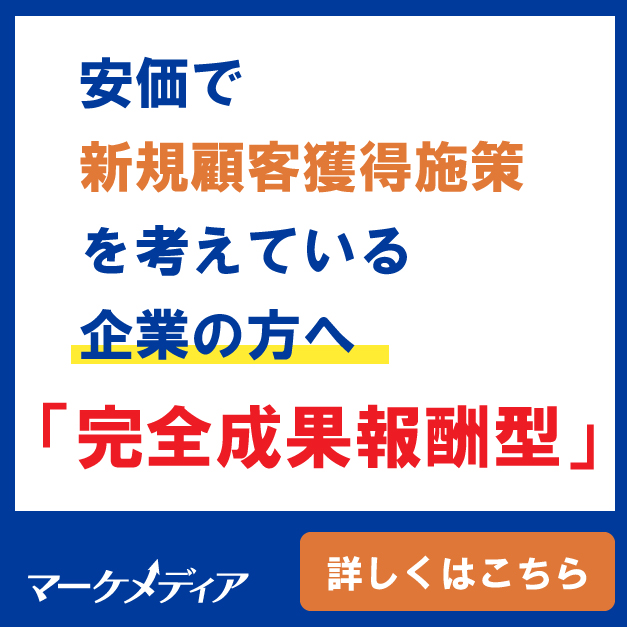MASA
0 Comments
 倉庫業界は近年注目を集めている業界です。成長力があって今後の拡大が期待されています。倉庫業界を知るためには倉庫会社の売上高ランキング上位の会社について知ることではないでしょうか。
倉庫会社の売上高ランキング上位の会社は業界に大きな影響を与える存在であり、現在の倉庫業界の方向性を指し示しているグループだといえるでしょう。
今回の記事では倉庫業界とはどういう業界なのかを解説し、倉庫会社の売上高ランキング上位の会社を5社挙げ、そのプロフィールを紹介します。法人営業で倉庫業界にアプローチを考えているみなさんは、ぜひ参考にしてください。
倉庫業界は近年注目を集めている業界です。成長力があって今後の拡大が期待されています。倉庫業界を知るためには倉庫会社の売上高ランキング上位の会社について知ることではないでしょうか。
倉庫会社の売上高ランキング上位の会社は業界に大きな影響を与える存在であり、現在の倉庫業界の方向性を指し示しているグループだといえるでしょう。
今回の記事では倉庫業界とはどういう業界なのかを解説し、倉庫会社の売上高ランキング上位の会社を5社挙げ、そのプロフィールを紹介します。法人営業で倉庫業界にアプローチを考えているみなさんは、ぜひ参考にしてください。

目次
倉庫業界とは?
 倉庫業の定義は「寄託を受けた荷物を倉庫で保管する営業形態」です。ひと言でいえば顧客の荷物を預かり保管することで報酬を得るビジネスモデルを指しています。
倉庫業界は運送業界と共に物流業界を形成しており、運送業と深い関係にあります。実際に倉庫業と運送業を兼業している物流会社も多く見られます。
倉庫業は公益性の高さから、かつて許可制が採用されていました。しかし現在では物流業務の効率化や国際競争力の向上を目的として登録制になっており、参入がしやすくなっています。
各自治体の運輸局が窓口となり、倉庫業の登録希望者はメールで申請可能となっています。
倉庫業の定義は「寄託を受けた荷物を倉庫で保管する営業形態」です。ひと言でいえば顧客の荷物を預かり保管することで報酬を得るビジネスモデルを指しています。
倉庫業界は運送業界と共に物流業界を形成しており、運送業と深い関係にあります。実際に倉庫業と運送業を兼業している物流会社も多く見られます。
倉庫業は公益性の高さから、かつて許可制が採用されていました。しかし現在では物流業務の効率化や国際競争力の向上を目的として登録制になっており、参入がしやすくなっています。
各自治体の運輸局が窓口となり、倉庫業の登録希望者はメールで申請可能となっています。
倉庫業の分類
倉庫業とひと口にいっても、いくつかの種類があります。代表的な倉庫業の種類は以下の3つです。- 普通倉庫業
- 冷蔵倉庫業
- 水面倉庫業
- 一類倉庫
- 二類倉庫
- 三類倉庫
- 貯蔵槽倉庫
- 野積倉庫
- 危険品倉庫
- トランクルーム
倉庫業の主な業務内容
倉庫業の主な業務内容は、顧客から預かった商材を倉庫に収めてから保管し、出荷するまでの一連の業務です。 基本的な業務フローは、以下のようになります。 第1段階:検品 仕入れ先や工場などから運ばれてきた商材の種類および数量の明細が合っているかどうかを検品します。機械製品の初期不良なども、この段階でチェックします。 第2段階:入庫 検品を通過した商材を管理番号なども確認した上で、所定の保管場所に運びます。 第3段階:保管 それぞれの商材に適した状態を整えて保管します。特に冷蔵品や冷凍品であれば、商材ごとに温度の管理が必要です。 第4段階:出荷準備 商材を出荷するための加工を施します。商材に応じて組み立てや個別包装、ラベル貼りなどさまざまです。 第5段階:ピッキング ピッキングリスト(注文書にもとづいて発行される出荷用リスト)を参照し、対象の商材を保管場所から取り出します。 第6段階:仕分け ピッキングが済んだ商材を、配送ルートなどの条件に従って仕分けます。 第7段階:出荷 仕分けが完了した商材を配送用のトラックに積み込み、いよいよ出荷です。倉庫業界の現状と動向
倉庫業界は近年のECの急速な拡大により、流通量が増加し、物流拠点が増加してきました。そういう動きを受け、商社や外資系企業が積極的に参入し、既存の倉庫会社も施設の新設および増床を進めています。 企業が倉庫を活用する需要に関しても、多くの業界がパンデミックによるマイナスの影響を受ける中で現状も拡大傾向です。それは巣ごもり需要や非対面非接触で買い物をしたいという需要を反映しているようです。倉庫会社売上ランキングTOP5
 倉庫業界の売上ランキングTOP5は以下のとおりです。
第1位:郵船ロジスティクス株式会社
第2位:株式会社近鉄エクスプレス
第3位:株式会社上組
第4位:三井倉庫ホールディングス株式会社
第5位:三菱倉庫株式会社
それぞれの倉庫会社のプロフィールを見ていきましょう。
倉庫業界の売上ランキングTOP5は以下のとおりです。
第1位:郵船ロジスティクス株式会社
第2位:株式会社近鉄エクスプレス
第3位:株式会社上組
第4位:三井倉庫ホールディングス株式会社
第5位:三菱倉庫株式会社
それぞれの倉庫会社のプロフィールを見ていきましょう。
倉庫会社売上ランキング第1位:郵船ロジスティクス株式会社
東京都品川区東品川に本拠地を構える郵船ロジスティクス株式会社は1955年に設立された、貨物輸送や倉庫業などを行う倉庫会社です。海上・航空貨物輸送と陸上輸送を組み合わせた輸送サービスや輸出入時の通関手続きなどを行っています。 また、集荷と配送の手配や貨物の梱包・ラベリング・仕分けなどの各種物流加工サービス、自社の各拠点での保管・配送サービスなども手がけています。 各国航空船舶会社の代理店業や物流コンサルタント、損害保険代理業なども展開しています。物流に関連するさまざまなサポート補助事業も展開しており、今後も同社の事業規模は広がっていくと考えてよいでしょう。 郵船ロジスティクス株式会社倉庫会社売上ランキング第2位:株式会社近鉄エクスプレス
東京都港区港南に本拠地を構える株式会社近鉄エクスプレスは1948年に創業された、航空運送代理店業および通関業、流通加工・作業サービスを営む倉庫会社です。 具体的には航空、海上、鉄道による貨物利用運送事業、一般貨物自動車運送業及び貨物自動車利用運送業、産業向けソリューションなどを手がけています。 海外の倉庫市場でもグローバル展開をしており、外資系企業である荷主に対して盤石な顧客基盤を持っている倉庫会社といえるでしょう。海外顧客の積極的な新規開拓をおこなってきた賜物です。ロジスティクス分野においても積極的で、国際海上貨物、国際航空貨物も取り扱っています。 株式会社近鉄エクスプレス倉庫会社売上ランキング第3位:株式会社上組
兵庫県神戸市中央区浜辺通に本拠地を構える株式会社上組は1947年に設立された、港湾荷役やコンテナターミナルの運営および貨物自動車運送などを手がける会社です。 港湾運送の分野では最大手でもあり、倉庫と運送を組みあわせた総合物流をおこなっています。重量貨物輸送もおこなっており、国内外の産業機器や鉄道車両、発電プラントや化学プラント機器などの大型貨物の輸送および据付を手がける、インフラ整備にも関わりのある会社です。 店舗や住宅などの建築も手がけているので、その方面のノウハウも活かされています。これらの複数の事業を展開する同社は物流ネットワークを構築するための基礎能力を持つ、堅実な倉庫会社といえるでしょう。 株式会社上組倉庫会社売上ランキング第4位:三井倉庫ホールディングス株式会社
東京都港区西新橋に本拠地を構える三井倉庫ホールディングス株式会社は1909年に設立された、倉庫会社グループの経営戦略策定や経営管理を行う会社です。 三井倉庫株式会社・三井倉庫エクスプレス株式会社・三井倉庫ロジスティクス株式会社・三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社・三井倉庫トランスポート株式会社からなるグループ会社をまとめています。幅広い事業カテゴリーに進出しているのも同社の特徴で、港湾運送や不動産事業も積極的に展開しています。 他にはロジスティクス、グローバルエクスプレス、グローバルフロー、サプライチェーンソリューション、BPO、トランスポートネットワークなどが挙げられます。 三井倉庫ホールディングス株式会社倉庫会社売上ランキング第5位:三菱倉庫株式会社
東京都中央区日本橋に本拠地を構える三菱倉庫株式会社は1887年に創業された倉庫会社です。 倉庫事業を主力として展開していますが、包括的でグローバルな物流サービスを提供しています。具体的には倉庫・港湾運送・陸上運送・国際運送取扱の4分野におよび、ロジスティクスでも力を発揮する総合物流企業といえるでしょう。また、企業の物流アウトソーシング需要に応えます。 ほかにもデータセンター対応オフィスビルの開発・賃貸を中心に、商業施設も取り扱う不動産事業も手がけています。 三菱倉庫株式会社倉庫会社ランキングのまとめ
 倉庫業界は運送とともに物流業としての今後の躍進が期待できます。法人営業担当者のみなさんはここで紹介した倉庫業界の概要や売上上位ランキングを参考として、ぜひ有効な営業戦略を構築してください。
なお、法人データを無料で毎月100社までダウンロードできるBIZMAPSは、さまざまな属性や条件で企業を検索できます。営業戦略を確立するために、ぜひお気軽にご利用ください。
▼日本最大級の企業DB【BIZMAPS】で倉庫関連企業を探す
法人営業向けの、さまざまな業種の特集記事はこちらです。
大手不動産会社売上ランキング&法人営業担当者のための優良企業一覧
【法人営業向け】コロナ禍の業績回復を支援しよう!貸切バス会社一覧
【法人営業担当必見】非破壊検査会社の現状と将来!首都圏の会社一覧
東証一部が消えた?区分再編の背景を解説!元東証一部上場の企業一覧
東証一部からプライム市場への移行基準未達企業一覧【法人営業向け】
アウトソーシング・代行サービスの業界動向解説!売上トップ企業10社ご紹介
倉庫業界は運送とともに物流業としての今後の躍進が期待できます。法人営業担当者のみなさんはここで紹介した倉庫業界の概要や売上上位ランキングを参考として、ぜひ有効な営業戦略を構築してください。
なお、法人データを無料で毎月100社までダウンロードできるBIZMAPSは、さまざまな属性や条件で企業を検索できます。営業戦略を確立するために、ぜひお気軽にご利用ください。
▼日本最大級の企業DB【BIZMAPS】で倉庫関連企業を探す
法人営業向けの、さまざまな業種の特集記事はこちらです。
大手不動産会社売上ランキング&法人営業担当者のための優良企業一覧
【法人営業向け】コロナ禍の業績回復を支援しよう!貸切バス会社一覧
【法人営業担当必見】非破壊検査会社の現状と将来!首都圏の会社一覧
東証一部が消えた?区分再編の背景を解説!元東証一部上場の企業一覧
東証一部からプライム市場への移行基準未達企業一覧【法人営業向け】
アウトソーシング・代行サービスの業界動向解説!売上トップ企業10社ご紹介 
大阪生まれ神戸在住。経済学部卒業後、アパレル業界で営業から商品企画・広告プロモーションを経験。2018年副業でライターを始め、2019年に会社を退職しライターに。Webライティングと並行し電子書籍も鋭意出版中。
著者ページ:https://amzn.to/3J5CbjX
無料で使える企業検索サービス