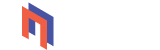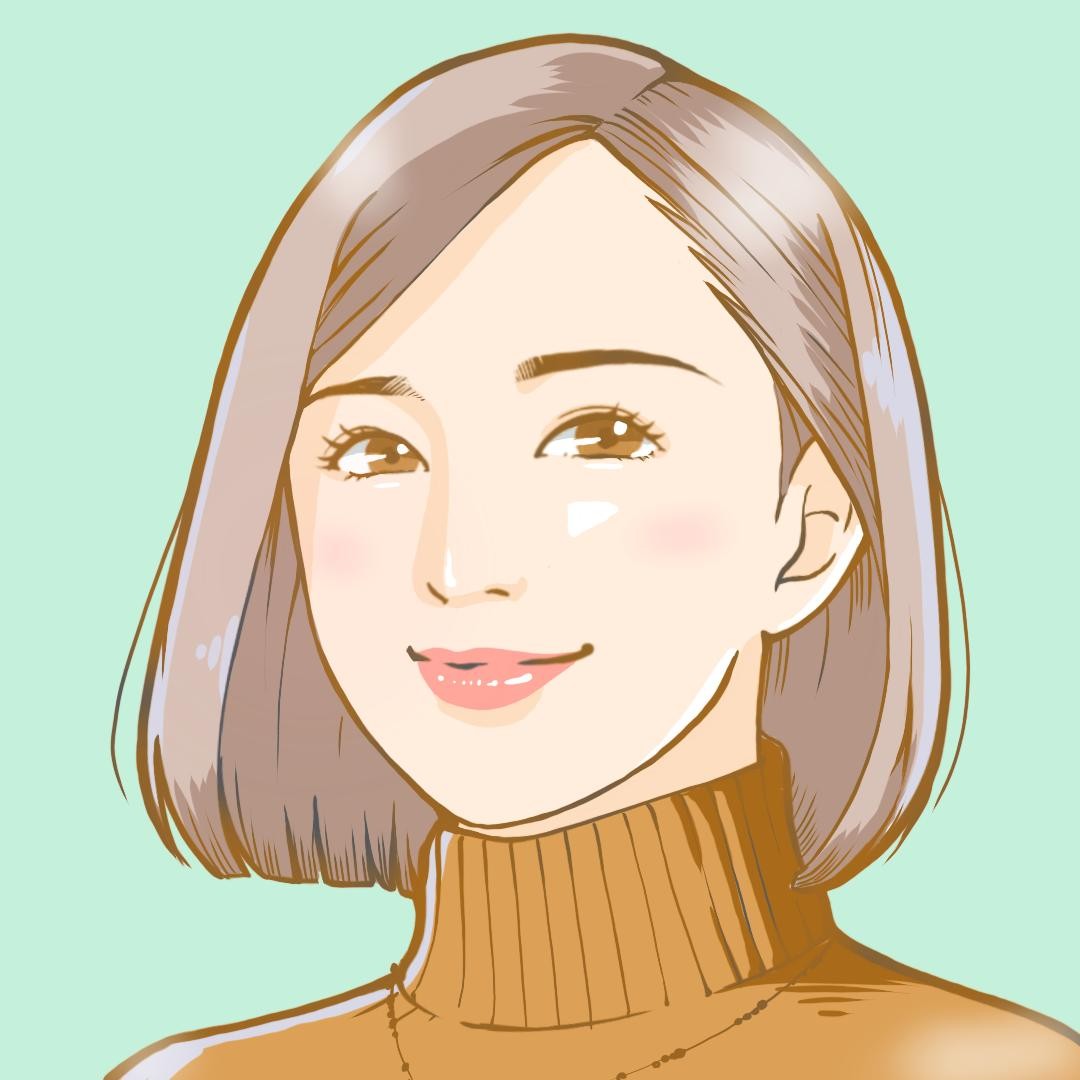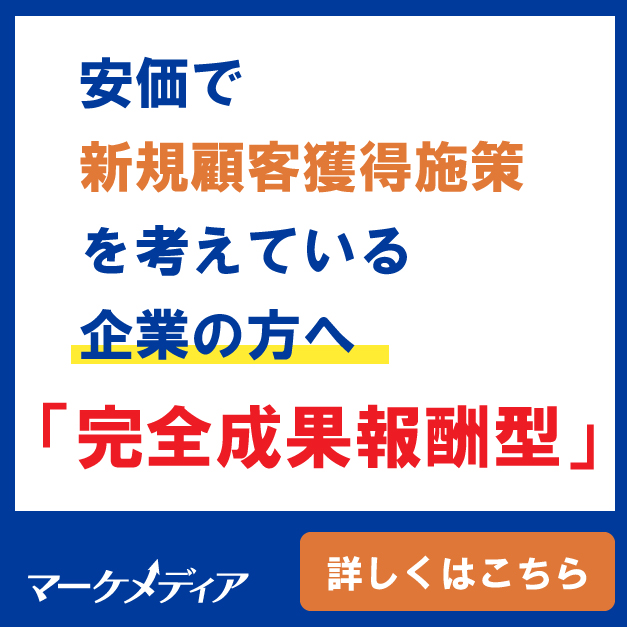風野ミユ
0 Comments
 一見関係がなさそうな、マーケティングとプレゼンテーション。
ですが、マーケティングの概念を学ぶ事で、プレゼンの質も向上するって知っていましたか?
プレゼンはただ資料を準備し、それを読み上げればよい単純なものではなく、マーケティング的ポイントを押さえることで効果的に聞き手にアピールすることが可能です。
この記事を読めば、基本的なマーケティングについての知識や、プレゼンに活かす方法を知ることができます。
プレゼンがいまいち苦手だ、何が問題か分からない、なんて方は、この記事を参考に1度自分のプレゼンについて見直してみてください。
一見関係がなさそうな、マーケティングとプレゼンテーション。
ですが、マーケティングの概念を学ぶ事で、プレゼンの質も向上するって知っていましたか?
プレゼンはただ資料を準備し、それを読み上げればよい単純なものではなく、マーケティング的ポイントを押さえることで効果的に聞き手にアピールすることが可能です。
この記事を読めば、基本的なマーケティングについての知識や、プレゼンに活かす方法を知ることができます。
プレゼンがいまいち苦手だ、何が問題か分からない、なんて方は、この記事を参考に1度自分のプレゼンについて見直してみてください。

目次
マーケティング知識を活かしてプレゼンの質を上げる
マーケティングがプレゼンに通じるのは、ユーザーに選ばれるため様々な工夫を凝らすマーケティングの考え方が、プレゼンにおける「聞き手の興味を惹き行動を促す」という基本概念と重なるからです。 まずは、マーケティングとプレゼン、それぞれの基本をおさらいし理解を深めた上で、実際にマーケティング要素をプレゼンに活用する方法を見ていきましょう!マーケティングをプレゼンに応用すると効果的な理由
マーケティングとプレゼンにはお互い似た要素を含んでいるため、両方の知識を付けることでより効果的なプレゼンを準備することが出来ます。プレゼンテーションとは?
プレゼンテーションは、聞き手に商品やサービスを利用してもらう、提案を受け入れてもらう、など何らかの目的を持って行う情報伝達行為です。 その内容自体に重きが置かれている研究発表などとの違いは、プレゼンは何よりも聞き手目線で行われる点と聞き手のその後の行動を促すための手段だという点です。 つまり、どんなに綺麗にまとめられたスライドで、話術の巧みなスピーカーが話しても、聞き手が「素敵な発表だったな」という感想で終わってしまっては、プレゼンとしては失敗です。 聞き手が、実際に商品を利用してみよう、もう少し詳しく話を聞いてみよう、と次の行動に繋げることが重要です。マーケティングとは?
マーケティングの概念は「モノやサービスが売れる仕組みをつくる」ということです。 そのため、マーケティングには集客イベントやキャンペーン、広告、マスメディアでの宣伝や、SNSやウェブサイトを使ったオンライン集客など、かなり広範囲の要素が含まれます。 その多岐に渡る活動の根底には、その商品やサービスがユーザーに与えられる価値、ターゲット、アピール手段、ライバルの研究、差別化できるポイントなどのリサーチが欠かせません。 そのマーケティングのプロセスを応用することで、効果的なプレゼンをすることが出来ます。プレゼン準備の流れ【基本編】
 基本的なプレゼンテーションの準備の仕方は下の通りです。
・アイディアの整理
・資料の構成案を作成
・PPT(パワーポイント)の作成
・スクリプトの作成
・練習・修正
それぞれを詳しく見ていきましょう。
基本的なプレゼンテーションの準備の仕方は下の通りです。
・アイディアの整理
・資料の構成案を作成
・PPT(パワーポイント)の作成
・スクリプトの作成
・練習・修正
それぞれを詳しく見ていきましょう。
アイディアの整理
プレゼン準備において多くの人たちが時間を掛けているのが、パワーポイント(PPT)資料の作成と発表練習の部分ですが、実はこのアイディア整理こそ時間をじっくりかけて行う必要があります。 どんな目的(ゴール)でプレゼンをするのか、競合の発表内容はどんなものか、持ち時間は何分か、どんな聞き手が来るのか、などを整理した上でプレゼンの内容を組み立てていきます。 更に詳しいクオリティーをアップさせるポイントは後程解説します。資料の構成案を作成
アイディア整理が終わると、すぐにPPT資料作りに入ってしまう人もいますが、実際の資料を作り始める前に全体の構成案を作るようにしましょう。 それぞれのスライドの時間配分や、核となる内容を配置するポイントを確認して、プレゼンが聞き手の興味を惹く内容になっているか、最後までテンポの良い構成になっているかを確認しましょう。PPTの作成
パワーポイントを作成するときに、とにかくデザイン性を重視しがちですが、聞き手にとってはデザインよりも分かりやすさが重要です。 1つのスライドにいくつもの主張を詰め込んでしまったり、カラフルな色使いにしすぎて強調するポイントが掴みにくくなったりしないように、聞き手に内容を分かりやすく伝えるという意識を忘れずに作成していきます。スクリプトの作成
パワーポイント資料が完成したら、次は発表者が話す原稿を作成します。 実際に全て資料通り読み上げるタイプのプレゼンは、聞き手もそのことに気づくと、ナレーションには注意を払わなくなってしまいがちです…。 パワーポイントで視覚的に整理した方が良い内容、発表者が言葉で伝えた方が効果的に伝えられる内容を精査して、プレゼンを組み立てていきましょう。練習・修正
プレゼンは、準備段階の努力をどれだけしたかで、成功・失敗が決まってしまうとも言われています。 当日は原稿を出来るだけ見ることなく、聞き手の顔を見ながら余裕を持ってプレゼンを行うことができるように、とにかく練習が大切です。 また練習をしながら伝わりにくいと感じる部分や、表現が曖昧な部分が見つかれば、その都度訂正しながらプレゼンの改善を続けます。マーケティングを応用してプレゼンの質を上げる6つのポイント
マーケティングの知識を活かせば、プレゼンを飛躍的に改善できます!
①ターゲットの選定はとにかく徹底して行う
聞き手となるターゲットがどんな背景を持っていて、どんな問題を抱えているのか、どんな伝え方が最も有効なのかを最初に考える必要があります。 不特定多数のオーディエンスに向けてプレゼンを行う場合は、想定できる聞き手グループの特徴から強調した方が良い点や、必ず伝えておきたい点を洗い出します。 ターゲットの設定は、詳細であればあるほど、聞き手の求める内容の盛り込まれたプレゼンを行うことができます。 その時に利用できるのが、マーケティングで良く使われる手法の1つ、ペルソナの設定です。 ペルソナとは、ターゲットとしたい層の中に架空の人物を想定し、プロフィールや家族構成、趣味、行動パターンや価値観などを事細かに設定していきます。 ペルソナを設定すると、プレゼンテーションを準備しながら曖昧になりがちな軸を、しっかり据えることができるのがメリットです。 反対に、企業間の提案としてプレゼンを行う場合は、聞き手となる担当者の中の1人(キーパーソン)に焦点を当てて準備をします。 その人が理解がしやすいようにするにはどうすればいいのか、どんな内容であれば満足するのか、プレゼンを聞き終えた後にどんな行動が予測されるかを考えて構成していくのが効果的です。 プレゼンもマーケティングと同じく、相手(聞き手、ユーザー)のことを第一に考え準備を行う、という姿勢が基本です。 ▼あわせて読みたい マーケティングにおけるペルソナの役割とは?設定方法をBtoCとBtoBに分けて徹底解説②聞き手の共感を誘うストーリーを入れる
人は他人事だと思ってしまうと、その物事への思い入れが薄くなってしまうため、プレゼンにはストーリーを組み込んで、いかに聞き手の興味を惹くことが出来るかが重要です。 何か商品を買う際にも、最近ではインターネットやSNSで事前に調べてから購入する人が多いのではないでしょうか? 例えば、化粧品であれば平然と成分と使い方だけが記載されているホームページを見ても、ユーザーはその効果がイメージし辛く感じ、結局、他の人が紹介しているブログの内容や口コミを参考にすることも多いです。 肌荒れで悩んでおり常に帽子を脱ぐ事が出来なかった人が、敏感肌に優しい鎮静クリームを使って肌質が改善し自信を持って外出できるようになった、というストーリーがあれば、同じような状況で悩んでいる人の心にきっと響くことでしょう。 ストーリーの主人公は聞き手であることも忘れないようにしましょう。③他と差別化出来るポイントを強調する
マーケティングのリサーチ段階で行われるのが、ライバル(競合他社)の研究し、自社の強みをどうやってアピールしていくかを決定していくプロセスです。 コンペなどでは、他の発表者をおさえて自分のプレゼンを魅力的に感じてもらう必要があるからです。 差別化ポイントを探すには、他社と自社の徹底した研究が欠かせません。 聞き手が求める価値を提供するために、アピールすべきポイントをプレゼンの軸として構成していきましょう。 ▼あわせて読みたい マーケティングでの戦略的なポジショニングとは?ポジショニングマップの解説&成功事例集④タイトルで第一印象が決まる
意外と手を抜いてしまいがちなプレゼンタイトルの設定ですが、聞き手にとっての第一印象を決める部分であるため、意外と重要です。 マーケティングの手法のひとつであるキャッチコピーは広告やメルマガ、ウェブサイトなど幅広く利用されていますが、それは私たちが情報を取捨選択する行為が、実は時間をかけずにあっという間に行われているからなんです。 知りたいことがあってウェブ検索をした時に、1ページ目にズラッと出てきたサイトを瞬時にスキャンし、タイトルからある程度の内容を推測してクリックするサイトを決定しています。 情報が溢れている昨今では欠かせない存在となったキャッチコピーは、瞬時にその商品やサービスの特徴、アピールポイントを相手に伝えることができるという点で優れています。 これはプレゼンにも応用できる考え方で、1ページ目のタイトルを見た瞬間からどれだけ聞き手に興味を持ってもらえるかが重要です。 キャッチコピーの付け方を学んでみるのも、プレゼンスキルの向上に役立つでしょう。⑤とにかく聞き手目線を意識する
より詳しい内容を、プロの目線から伝えたいという思いで、プレゼンが専門用語だらけになってはいませんか? 聞き手は、自分が抱えている問題やどうにかしたいと思っている悩みの解決策を見つけるために、あなたのプレゼンを聞いている場合が多いです。 そんな時に理解のできない専門用語を連発されたり、自分に関係ない難解なシステムの説明をされても、正直なんの興味も持てないのです。 マーケティングと同じくプレゼンも、ユーザーファーストで行われるのが基本です。 分かりやすい言葉で、聞きやすい速度で、見やすい文字の大きさ・色の配色で、何よりも聞き手がスムーズに情報を受け取る事が出来るか、という視点を忘れないようにしましょう。 また、マーケティングでは、実際に商品やサービスを利用するお客さんの立場に立った検証テストが何度も行われています。 自分の思い込みだけでプレゼンの準備を進めてしまう事がないように、時には「違う視点からはどう見えるか」「専門知識のない人が問題なく理解できるか」などを立ち止まってチェックするようにしましょう。⑥シンプルに無駄を省く
 最後に少し注意すべきポイントになりますが、聞き手目線に合わせて丁寧な説明をしようとするあまり、説明が長くなってしまう事があります。
プレゼンの構成を考えるときには、「必要な事だけを伝える」というポイントを忘れないようにしてください。
聞き手はそのプレゼンで紹介されているサービスや商品に興味があるのであって、発表者のあなたのトーク力を楽しみにしているわけではありません。
緩急をつけて、聞き手にポイントが伝わりやすい話し方をすることが大事です。
また、パワーポイントのスライドに関しても必要以上にカラフルにしたり、アニメーションを入れすぎたりしてしまうと、ごちゃごちゃしてしまい逆効果になってしまう場合があります。
1つのスライドに1つの内容を分かりやすくまとめ、全て文字で記入するのではなく、口頭で問題ない部分は口頭ナレーションで説明すれば、見る人に伝わりやすいスライドが出来上がります。
色彩に関しては使う色のトーンを合わせたり、色の数を限定してスライドを作成するのも有効です。
最後に少し注意すべきポイントになりますが、聞き手目線に合わせて丁寧な説明をしようとするあまり、説明が長くなってしまう事があります。
プレゼンの構成を考えるときには、「必要な事だけを伝える」というポイントを忘れないようにしてください。
聞き手はそのプレゼンで紹介されているサービスや商品に興味があるのであって、発表者のあなたのトーク力を楽しみにしているわけではありません。
緩急をつけて、聞き手にポイントが伝わりやすい話し方をすることが大事です。
また、パワーポイントのスライドに関しても必要以上にカラフルにしたり、アニメーションを入れすぎたりしてしまうと、ごちゃごちゃしてしまい逆効果になってしまう場合があります。
1つのスライドに1つの内容を分かりやすくまとめ、全て文字で記入するのではなく、口頭で問題ない部分は口頭ナレーションで説明すれば、見る人に伝わりやすいスライドが出来上がります。
色彩に関しては使う色のトーンを合わせたり、色の数を限定してスライドを作成するのも有効です。
まとめ
マーケティングとプレゼンは、聞き手やユーザーに次の行動を促すという点で共通した概念を持っているため、マーケティングの知識を応用することでプレゼンの質を上げる事ができます。 マーケティングで重要視されるターゲットの選定、市場・競合(ライバル)の調査、プロモーション手段の検討、ユーザーの利用しやすいサービスの提供など、そのプロセス1つ1つがプレゼンを準備する時に役立ちます。 この記事で紹介している「マーケティング的思考を応用したプレゼンの質を上げるポイント」を実践して、プレゼンの改善をしてみてください。 ▼あわせて読みたい マーケティング戦略に有効なSWOT分析は他手法と併用+クロス分析で最強のアプローチに! マーケティングの要となるセグメンテーションとは?成功事例も紹介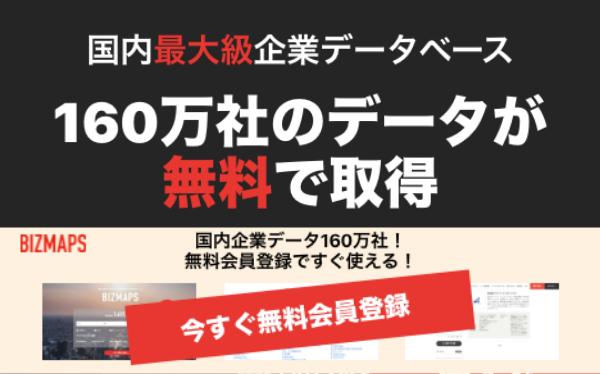
無料で使える企業検索サービス