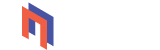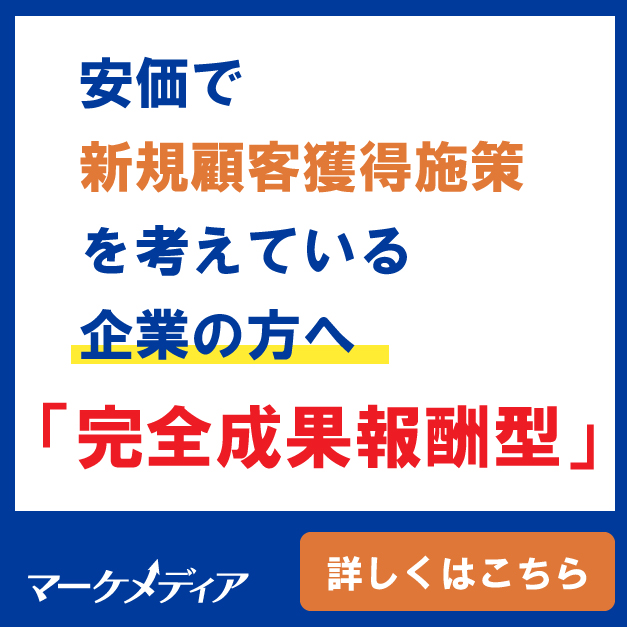BIZMAP 編集
0 Comments

目次
製紙業界のバリューチェーン
製紙業界の取り扱い商品・サービスの特徴
製紙業界の製品は、紙と板紙に大別されます。厳密な区分はないものの、単位面積当たりの質量が軽いものが紙、重くて厚くコシがあるものが板紙です。 生産量の比率は紙と板紙で6:4程度となっており、紙では印刷・情報用紙、新聞用紙、板紙では段ボールとしての用途がメインとなっています。 製紙業界の製品の特徴としては、リサイクルが一般的になっている点が挙げられます。国内の紙・板紙の古紙回収率は80%を越えており、これは世界でもトップレベルの回収率です。また再使用される古紙利用率は64%で、特に段ボールを含む板紙は90%以上のリサイクル率となっています。 古紙のリサイクルは加工工程が複雑ではあるものの、技術の発展とともに効率化されてきており、原材料の安定調達から国際競争力の強化にもつなげられるため、各社がともに注力しています。 また紙・板紙は、物流コストが大きいのも特徴です。特にパルプや段ボールなど、空洞の大きい製品に関しては物流効率が悪いため、産地消費が一般的になっています。このことからも、パルプの製造から製品までを一貫して手がけることは、効率化につながるといえるでしょう。 また、段ボールの工場は大口ユーザーに近接した立地に構えるなど、物流コストの削減も各社が注力する領域となっています。製紙業界のビジネスモデル
製紙業界は典型的な装置型産業で、大手企業であれば毎年1,000~4,000億円の大きな設備投資が必要です。 また製品の差別化要素が少なく、薄利多売の構造であることから、いかに大量生産によってコスト優位を築いて価格競争に勝っていくかが重要な要素となります。このため製紙業界は大手企業による寡占状況となっており、新規参入の可能性はほぼ考えられません。また買い手に対しては、寡占産業となっているために原材料調達コストを比較的川下に転嫁しやすく、交渉力は強くなっています。 一方で近年の人口停滞や代替品としてのタブレット端末の浸透は、紙媒体離れを加速させています。こうした社会動向を受けて紙の需要が減少していることが、製紙業界における市場縮小の要因です。 また売り手に対しては、原材料の木材の海外依存と、燃料としての原油価格がリスクとなっています。そのため各社川上の植林事業への投資や、工場における省エネ化への投資をおこなってリスク分散を図っている状況です。製紙業界の主要成功要因
業界の特徴を考慮した製紙業界のKFS(主要成功要因)として、大きく2つの要因が挙げられます。 ひとつめは、規模の拡大による効率化です。現在までの再編動向を踏まえると、同業を吸収することで物流や原料の一括調達といった規模の経済を確保することが、収益増加に向けた方策であったことが分かります。 また現在の状況では、川上と川下への交渉力を維持するためにも規模の拡大は有効で、原料調達と最終品製造といった上下方向への進出投資も、リスクの低減につながるため重要となっています。 さらに各社は海外進出を志向している一方で国内の植林にも注力しており、原材料の国内比率を上昇させることで、国内消費に対する供給の安定化を目指すことも有効な手段と考えられている状況です。 ふたつめの主要成功要因は、成長分野を見極めた選択と集中です。新聞離れのような社会動向に代表されるように、製紙業界においても成長分野と衰退分野が顕著に表れるようになっています。例として、インターネット通販の台頭にともなう堅調な段ボール消費や、新興国では生活水準の向上にともなうトイレタリー用品の需要増加なども挙げられます。 製紙市場は国内では長期的には縮小が予測されている市場ではありますが、このように成長分野は存在するため、所有する経営資源に見合ったかたちで成長領域にリソースを投入するというような選択と集中が重要です。 また先端技術として、木材繊維を利用した強度が高く軽い繊維素材「セルロースナノファイバー」など、新たな市場を開拓できる製品も開発されており、技術による付加価値を確保することで差別化を狙っていくことも考えられるでしょう。製紙業界の市場規模・トレンド
製紙業界を取り巻く環境
マクロ経済の影響を受ける要因
製紙業界がマクロ経済の影響を受ける要因としては、為替、新興国市場の成長、原油価格の高騰などが挙げられます。原材料の木材を輸入に依存しているため、円高時は国内志向が強く、他の産業に比べ海外進出が少ない業界でした。しかし近年の円安による原材料輸入コストの高騰を受けて、参入各社は新興国市場へ成長余地を求めるようになっています。 また原油価格の高騰もコスト要因となっており、燃料価格対策としてRPF(Refuse Paper and Plastic Fuel)を利用したボイラーなど、燃料転換や省エネルギー化に向けた設備投資が盛んにおこなわれるようになりました。 そのほか特筆すべきは、米中貿易摩擦により、中国で日本産古紙の特需が生まれたことです。中国は米国産古紙を多く輸入していましたが、対米報復関税が発動された2018年から、代替として日本の古紙が大きく需要を増しています。追い風となる要因がある一方で、中国当局は環境対策のため2020年に廃棄物の輸入を禁止するなど、日本の製紙業界は今後も中国当局の動向を注視すべきでしょう。製紙業界の今後の展望
製紙業界の今後の展望としては、大きく分けて次の3つのシナリオが考えられます。- 一層の業界再編
- 海外展開の加速
- プロダクト・プロセスイノベーションによる業界構造の変化
一層の業界再編
まず挙げられるのが、ペーパーレス化や人口停滞にともなう長期的な国内市場の縮小と、それによって起こる製紙業界の一層の再編です。 市場の縮小が顕著に表れるようになると、各社生き残りに向けた価格競争が激しくなり、コスト優位を築くことを目的とした更なる規模の経済の獲得に動いていくことが考えられます。 実際に王子ホールディングスは、2006年に業界5位の北越紀州製紙を買収しようと試みたものの、実現しませんでした。このような動きが、今後の市場環境を受けて、再び活発化していく可能性が考えられます。海外展開の加速
ふたつめは、新興国市場の成長にともなう海外展開の加速です。 長期的な国内市場の縮小もそれを後押しし、各社成長余地を求めて海外展開に注力するようになると考えられます。 たとえばすでに王子ホールディングスは海外売上比率の上昇がめざましく、日本製紙に関しても、中期経営計画において海外売上比率19%を目指すと発表しています。プロダクト・プロセスイノベーションによる業界構造の変化
最後は、新素材やリサイクルなど技術革新にともなう、プロセスイノベーション・プロダクトイノベーションがもたらす業界構造の変化です。 製紙業界の現在のおもな仕向け先業界は、新聞や印刷、トイレタリーメーカーですが、新たな産業に転用できる素材が開発されることで、新規市場の開拓が起きる可能性があります。 いま注目されている木材由来の「セルロースナノファイバー(CNF)」は炭素繊維の代替品になるといわれており、カーボン素材が使われるような産業への進出も考えられるでしょう。 経済産業省は2030年のCNF市場は1兆円規模に成長すると見込んでおり、積極的な産官学連携の支援を始めています。 ほかの技術としては、王子ホールディングスは製紙業の強みである抄紙技術を活かして、木材パルプだけでなくガラス繊維やプラスチック繊維、炭素繊維から紙を作る技術を開発。これにより、紙同様の薄さや成形自由度の高い素材を供給することができるため、新たな工業利用に期待がもたれています。 また、古紙利用率の上昇や古紙を利用しても上質な紙に加工できる技術など、リサイクル技術のさらなる進展によって、木材などの原材料への依存度が下がっていくことも考えられるでしょう。原材料調達が業界の大きなリスク要因のひとつですが、それを解決するプロセスイノベーションは、業界構造を変えるポテンシャルを秘めているのです。暮らしに欠かせない製紙業界の動向に注目
製紙業界は成熟している業界ですが、ペーパーレス化などによる紙の需要減もあり、さまざまな試行錯誤を実施しています。 いずれにしても、紙は私たちの生活に欠かせないものなので、今後の製紙業界の動向には注目しておきたいところです。 製紙業界に属する企業情報はBIZMAPSで簡単に入手できるので、ぜひチェックしてみてくださいね。 ▼トレンドや動向が分かる法人営業ハックの業界特集はこちら! 素材業界とは?構造から企業が抱える課題、今後の動向まで研究し解説します! 製造業界の現状と課題とは?今後の展望や売上ランキングTOP10も紹介! ▼BIZMAPSのオリジナルタグを元にした企業特集はこちら! 経団連とはどんな団体?日本経済連合会の概要と代表的な企業会員一覧 メディアレーダーは自社の資料を多くの人に見てもらえる媒体です ▼法人営業ハック注目の企業特集はこちらから! 段ボール製造会社3選!業務内容や段ボールの種類についてもご紹介 東証一部からプライム市場への移行基準未達企業一覧【法人営業向け】 農業に参入する会社が増えている?法人営業の新たなリード候補に!無料で使える企業検索サービス